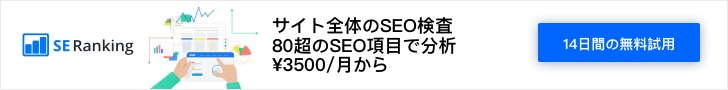Google「検索エンジンスターターガイド」をSEO施策別に解説-2023年12月03日
SEOには大きく分けて、外部SEO対策、内部SEO対策、コンテンツSEO対策があります。
ただし厳密には分類できない施策もあります。
たとえば内部SEO対策には、技術的なSEOもある一方、コンテンツSEOに近い施策もあります。
SEOを行うには、次の情報を参考にするのがよいでしょう。
- 検索エンジンが開示・提供する方針やガイドライン
- アクセス解析やキーワードツール、SEOツールから得られるデータ
- 検索エンジンが開示・提供するニュースリリースやブログ、SNS投稿等
検索エンジンが開示・提供する方針やガイドライン
検索エンジンの公式のガイドラインとしては、Googleでは「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」、Bingでは「Bingウェブマスターガイド」などが知られています。
その他のリソースとしては、次のものがあります。
Google 検索セントラルのブログ
Google 検索セントラルの Twitter
Google 検索セントラルの YouTube チャンネル
ここでは、SEOの第一歩として目を通しておくべき「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」について、外部SEO対策、内部SEO対策、コンテンツSEO対策に分類して解説します。
「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」の対象読者は、「企業の経営者、いくつものウェブサイトの所有者、ウェブ代理店の SEO 専門家、Google 検索の仕組みを学んで SEO を改善したいとお考えの個人の方など」とされています。
SEO会社に依頼する場合でも、WEB事業の担当者、経営陣、個人のWEB管理者などは、内容をよく知っておくのが良いでしょう。
Googleのおすすめの方法を知り、それに基づいてWEB制作、コンテンツ制作を行うことが、SEO効果を高めるための重要な参考になるでしょう。
「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」に基づく外部SEO対策
Google Search Consoleにサイトを登録する
「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」の「サイトを Google に表示するには」では、
「Google Search Console では、コンテンツを Google に送信し、Google 検索での状況を確認するためのツールを提供しています。」
として、WEBサイトを登録することを推奨しています。
Google Search Consoleを使えば、次のことがわかります。
- 所有するウェブサイトが Google に表示されているか?
- ユーザーに質の高いコンテンツを提供しているか?
- 所有するローカル ビジネスが Google に表示されているか?
- ウェブサイトのコンテンツにどのデバイスからでも速く簡単にアクセスできるか?
- 所有するウェブサイトは安全か?
サイトマップの送信
スターターガイドの「Google がコンテンツを見つけられるようにする」では、最適な方法としてサイトマップの送信をあげています。
サイトマップとは、サイト上の新しいページまたは変更されたページについて検索エンジンに伝えるための、たとえば「index.xml」「sitemap.xml」のようなファイルです。
詳しくは、サイトマップを作成して送信する方法を確認し、WEBページがGoogleにインデックスされやすくなるようにしましょう。
クロールさせたくないページをrobots.txtで検索エンジンに伝える
robots.txtを使って、GoogleやBingなどの検索エンジンのクローラを制御することができます。
アクセスされたくないページは、robots.txtに記述することで、ブロックすることが可能です。
robots.txtは、WEBサイトのルートディレクトリに配置します。
また、chatGPTなどの学習にWEBサイトのデータを利用されたくない場合の制御を記述することもできます。
記述例
User-agent: googlebot
Disallow: /admin/
Disallow: /cgi-bin/
検索エンジンの検索結果に表示してほしくないページや、意味のないページやディレクトリは、robots.txtでクロールされないようにするとよいでしょう。
その他の方法では、ページごとのhead内にnoindexタグやnofollowタグを使用する方法、高いセキュリティが必要なディレクトリはベーシック認証などで保護する方法があります。
被リンク
スターターガイドの「ウェブサイトを宣伝する」においては、
「サイトへのリンクの大部分は、ユーザーが検索やその他の方法でコンテンツを発見してそのコンテンツにリンクするにつれて、徐々に増えていきます。」
としています。
外部からの被リンクは、今日でもSEOにおいて重要な施策です。
しかし不自然な被リンクなどはスパムとして扱われるリスクがあり、「スパムに関するポリシー」で説明されています。
スターターガイドでも、「避けるべき事項」として、
「自分のトピック分野に関連するすべてのサイトに対してリンク リクエストをスパム的に送信する。」、
「PageRank の獲得を目的に別のサイトからリンクを購入する。」
ことがあげられています。
効果の高い被リンクは、自然に集まるリンク、関連あるサイトから張られるリンク、権威あるサイトから張られるリンクなどです。
自作自演リンクなどは検索エンジンに見破られやすいため、現在では基本的にはやらないほうがよいでしょう。
ただし自社で運営している別サイトから、ごく普通に自然に紹介するリンク程度は問題ありません。
自分で被リンクを集めるとすれば、下記の程度かと思われます。
- 自社の関連サイト、ブログ等からの過度ではないリンク
- 業界団体、グループ等、関連する精鋭サイトからのリンク
- Googleビジネスプロフィールや、地域の代表的なサイトからのリンク
- SNSなどからのリンク
作成したコンテンツを他の人に知らせる
スターターガイドでは、
「新しいコンテンツを効果的に宣伝すれば、同じテーマに関心を持っているユーザーに発見されるのが早くなります。」
としています。
一方で、
「ただし、このガイドでご紹介した他の注意点と同様に、以下のおすすめの方法を極端に行うと、実際にはサイトの評判を傷つける可能性があります。」
とも注意喚起しています。
WEBサイトのコンテンツを宣伝するには、SEOや広告のほか、SNS投稿が代表的です。
それ以外にも、オンラインコミュニティ、RSSフィード、メルマガ、オフラインでの宣伝を利用する方法などがあります。
スターターガイドの「避けるべき事項」では、次の項目があげられています。
- 新しい小さな分量のコンテンツを作成するたびに宣伝する(大きくて興味を引くコンテンツを宣伝しましょう)。
- コンテンツがソーシャル メディア サービスの上位に表示されるように人為的に操作する手法をサイトに適用する。
- サイトの関連コミュニティのユーザーにアプローチする
Googleビジネスプロフィールに登録する
Googleビジネスプロフィールは、企業や個人事業者が、ビジネスのプロフィールや所在地を登録し、googleマップ上に表示させるとともに、検索での露出が可能になるものです。
特に地域に密着した店舗や企業などの集客に効果的です。
Googleビジネスプロフィールでは、住所、電話番号などの連絡先のほか、営業時間や休日、メニューや価格、最新情報、写真、Q&Aなどの掲載や口コミの収集が可能です。
SNSでの情報配信
facebook、X(旧Twitter)、InstagramなどのSNS、YouTubeなどの動画配信サイトでは、自社の情報配信や、さまざまなコンテンツ配信ができます。
配信内容にWEBサイトの情報やURLなどを掲載できるほか、それぞれのSNSのプロフィール欄、概要欄などにも一定の情報が掲載できます。
SNSではユーザーとのコミュニケーションがとれるほか、他のユーザーによる言及を通じて情報の拡散が期待できます。
ユーザーによる言及を「サイテーション」といい、被リンクが得られないか、nofollowの付いた被リンクで直接的な被リンク効果は得られない場合でも、SEO効果があるとされています。
実際の集客やブランド価値の向上にも効果があるでしょう。
検索のパフォーマンスとユーザーの行動を分析する
SEO対策には、検索順位のチェックや、アクセス解析等によるユーザー行動の分析が不可欠です。
スターターガイドでは、次のように説明しています。
「Googleなどの主要な検索エンジンでは、ウェブサイトの所有者向けに、検索エンジンでのパフォーマンスを分析できるツールが提供されています。Google の場合は、そのようなツールとしてSearch Consoleをご用意しています。」
Search Consoleを使えば、Googleがページをインデックスしているか、外部からの被リンク、被リンクされているアンカーテキストなどの、外部SEO施策に有効な情報を確認することができます。
また、Search Console Insightsを使えば、WEBサイト内でアクセスされているページや、ユーザーが使った検索キーワードなどサイト集客の経路を知ることができます。
SEO対策は、施策の実施と、効果の検証の繰り返しともいえます。
Search Consoleでは、その他にも次のことが可能です。
- Googlebotがクロールできなかったサイトの部分を確認する
- サイトマップをテスト、送信する
- robots.txtファイルを分析、生成する
- すでにGooglebotにクロールされたURLを削除する
- 使用するドメインを指定する
- title と description meta タグを使用して問題を特定する
- サイトへのアクセスに使用された上位の検索クエリを把握する
- Google からのページの見え方を確認する
- スパムポリシー違反に関する通知を受け取り、サイトの再審査をリクエストする
なお、Microsoftが提供するBing Web マスターツールでも、同様に検索エンジンBingについての情報を得ることが可能です。
「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」に基づく内部SEO対策
検索エンジンとユーザーがページを読めるようにする
スターターガイドの「Google(とユーザー)がコンテンツを理解できるようにする」の項目では、検索エンジンがデータを収集するためのGooglebot がページをクロールするときに、平均的なユーザーが見るのと同じ状態でページを参照できる必要があるとしています。
最適なレンダリングができ、インデックス登録されるためには、WEBサイトで使用しているJavaScriptファイル、CSSファイル、画像ファイル等に検索エンジンのロボットがアクセスできる必要があります。
robots.txtファイルでクロールを許可しない場合には、そのファイルはインデックスされず検索結果に出ないため、注意が必要です。
ユーザーにも当然に、ページを正しく読み込んで閲覧できるようにしていなければなりません。
なお、検索エンジンがページをどのように認識してレンダリングしているかは、Sraech Consoleno「URL検査ツール」を使用して確認することができます。
各ページに固有のタイトル(Title)を付ける
ページのタイトルには、各ページのHTMLのhead内に記述され、検索結果のタイトルやブラウザのメニューバーなどに表示される、titleタグで指定されるタイトルがあります。
ページのコンテンツに記載されるタイトルは通常はh1などの見出しで、これとは異なります。
HTMLのtitle要素に記述されたタイトルが、通常は検索結果のタイトルリンクとして表示されますが、Googleの方で別のタイトルを生成することがあります。
文字数を30文字程度までに収める、ページの内容を簡潔、的確に表したタイトルにすることで、記載した通りのタイトルが表示されやすくなります。
スターターガイドにもあるように、title要素には、「ウェブサイトや企業の名前を表示し、さらに企業の所在地や主力商品またはサービスなど、重要な情報の一部を加えられます。」
SEOのヒント
「スターターガイド」では、title要素についての避けるべき事項も解説されています。これらハSEOにマイナスの効果をもたらす可能性もあり、注意しましょう。
・ページのコンテンツと関連のないテキストを、title要素で使用する。
・サイトのページ全体または多数のページにわたり、すべてのtitle要素に1つのタイトルを使用する。
・ユーザーにとって有益ではない、極端に長いテキストをtitle要素で使用する。
・title要素に、不要なキーワードを乱用する。
meta descriptionタグを使用して、検索結果のスニペットを制御する
メタタグは、各ページのHTMLのhead内に記述されるタグで、meta description(概要)、meta keywords(キーワード)などがあります。
キーワードは今日のSEOにほぼ意味がありませんが、メタディスクリプションタグは、検索結果のタイトルの下のスニペット(概要)に表示されることもあるため、記述することがよいでしょう。
CMSのテンプレートにより、各ページごとのタイトルやメタデスクリプションを自動的に生成する方法もあります。
meta descriptionタグに記載した内容は、Google検索結果でページのスニペットとして使用される可能性があります。
ページ内のコンテンツに、検索キーワード(クエリ)と関連のあるテキストがある場合には、その関連部分が検索結果に表示されることもあります。
各ページのメタディスクリプションは、120文字程度までに収め、ページの内容を適切に要約し、表示されたときにユーザーがクリックしやすいような内容にすることが秘訣です。
SEOのヒント
「スターターガイド」では、meta description要素についての避けるべき事項も解説されています。これらハSEOにマイナスの効果をもたらす可能性もあり、注意しましょう。
・ページの内容と関連のないmeta descriptionを記述する。
・「これはウェブページです」や「野球カードについてのページ」のような一般的な説明を使用する。
・サイトのページ全体または多数のページにわたり、すべてのmeta description要素に同じ概要を記載する。
meta description要素に、不要なキーワードを乱用することも避けるべきでしょう。
見出しタグを使用して重要なテキストを強調する
見出しタグはページ内のコンテンツに、h1, h2, h3, h4などのHTMLタグで囲む大見出し、中見出し、小見出しのことです。
スターターガイドでは、「わかりやすい見出しを使用して重要なトピックを示すと、コンテンツの階層構造が作成され、ユーザーがドキュメント内を移動しやすくなります。」としています。
見出しは、ページコンテンツをトピックごとに分け、h3はh2の下に置くなどの、ツリー構造のような文書構造にします。
h1タグはページ全体のタイトルに使用することが一般的です。
見出しには、不自然、過度にならないように検索キーワードを使用するのがよいでしょう。
SEOのヒント
「スターターガイド」では、見出し要素についての避けるべき事項も解説されています。これらハSEOにマイナスの効果をもたらす可能性もあり、注意しましょう。
・ページの構造を定義する際に、効果的でないテキストを見出しタグで囲む。
・emやstrong のような他のタグのほうが適している場所で見出しタグを使用する。
・見出しタグのサイズを不規則に変える。
・ページ全体で控えめに見出しを使用する
・ページで見出しタグを過度に使用する。
・非常に長い見出しを使用する。
・構造を示すためではなく、テキストの書式を整える目的で見出しタグを使用する。
SEOのヒント
「スターターガイド」にはありませんが、ページ内の文書構造や、コンテンツの意味を検索エンジンに伝えるには、メインコンテンツやナビゲーション、広告などを、HTML5のタグで意味を伝えることが有効と考えられます。
header, footer, nav, main, aside, article, sectionなどのタグです。navはナビゲーション、mainはメインコンテンツ、asideは広告などの補助コンテンツ、articleは記事全体、sectionは記事内の章などのトピックを示します。
構造化データのマークアップを追加する
構造化データは、HTML中に記述し、ユーザーではなく検索エンジンに対し意味を伝えるためのデータです。
スターターガイドには次のように説明されています。
「構造化データとは、検索エンジンがページの内容をより適切に認識できるように、検索エンジンにコンテンツを伝えるためにサイトのページに追加できるコードです。検索エンジンではこの解釈を利用して、検索結果にコンテンツを効果的に(目を引くように)表示できます。つまり、そのサイトのビジネスがターゲットとするお客様を引きつけるのに役立ちます。」
「たとえば、オンライン ショップで個々の商品ページをマークアップすると、Google がページの特徴(自転車、価格、カスタマー レビューなど)を理解しやすくなります。関連するクエリの検索結果でスニペットにその情報が表示されるようになります。これらの結果を『リッチリザルト』といいます。」
構造化データには、次のようなものがあります。
販売している商品
お店やサービスの所在地
商品やビジネスに関する動画
営業時間
イベント情報
レシピ
会社のロゴなど
構造化データは、サポートされている表記マークアップとともに構造化データを使用して、記述します。
HTMLに直接記述したり、CMSやそのプラグインで記述したりできます。
マークアップ支援ツールのようなツールを使用することもできます。
WEBサイトの階層を整理する
WEBサイトは、ディレクトリ構造などを整理して、重要な検索キーワード(クエリ)ごとに分類してコンテンツを配置し、階層構造にすることが重要です。
内部リンクを下層から中層、のサブディレクトリ、中層から上層に集中し、トップページが最重要キーワードに対応するのが一般には理想です。
スターターガイドには、次の記述があります。
「すべてのサイトにホームページ(ルートページ)があります。通常はサイトで最もアクセスの多いページで、ユーザーにとってナビゲーションの出発点となります。サイトに少数のページしかない場合を除いて、一般的なルートページからより具体的なコンテンツを含むページにユーザーをどのように誘導するか検討してください。特定のトピック領域に関するページが十分にあり、関連するページを紹介する別のページを作成するのが適当かどうか(たとえば、ルートページ -> 関連するトピックの一覧 -> 特定のトピック)、何百点もの異なる商品があり、複数のカテゴリとサブカテゴリのページに分類する必要があるかどうか、などを検討してください。」
WEBサイトのディレクトリ名・URLを整理する
スターターガイドの「検索エンジンによるURLの使用方法を理解する」の項目では、次の説明があります。
「検索エンジンがコンテンツをクロールしてインデックスに登録し、ユーザーに示すためには、コンテンツのまとまりごとに固有のURL が必要です。検索に適切に表示されるには、個別のコンテンツ(ショップ内の各商品など)や改変されたコンテンツ(翻訳や地域別のバリエーションなど)で個別のURLを使用する必要があります。」
サイトのコンテンツや構造に関連する単語を含むURLなど、意味のあるURLを使用すれば、利便性が増し、ユーザーも検索エンジンも理解しやすくなります。
また、URLは検索結果に表示されるため、簡潔でわかりやすいことも大切です。
Google はあらゆるタイプの URL 構造を(非常に複雑な URL であっても)適切にクロールできますが、URL をできるだけ簡潔にするために手間をかけることをおすすめします。
URL で単語を使用するは、サイトを閲覧するユーザーにとってより親切になります。
SEOのヒント
「スターターガイド」には、URLについての避けるべき事項も解説されています。
検索エンジンは複雑なURLでも理解できますが、次のような点に注意が必要とされています。
・こと不必要なパラメータやセッションID を含む長いURLを使用すること。
・page1.htmlのような一般的なページ名にすること。
・baseball-cards-baseball-cards-baseballcards.htmlのように過剰なキーワードを使用する。
・dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.htmlのようにサブカテゴリを深くすること。
・含まれているコンテンツと関連のないディレクトリ名を使用すること。
・ユーザーによってリンクするURLが異なること。
SEOのヒント
同一ページに複数のURLで到達できると、そのページに対する検索エンジンの評価が複数のURLに分散してしまうおそれがあります。
たとえばwww を含むバージョンと www を含まないバージョンや、httpsとhttpの別、ホスト名の後にある末尾のスラッシュ(/)の有無などです。
これらは、「.htaccess」ファイルを設置して、301リダイレクトにより統一する必要があります。
URLが変更になったときも、301リダイレクトによる転送ができます。
一方、たとえばブログの個別記事とカテゴリーページのように、ページの多くの部分が共通しているときなどに、ページに「rel="canonical"」のリンク要素を使用して、優先されるべきページを指定する方法もあります。
わかりやすいナビゲーションを設置する
スターターガイドでは、WEBサイトのナビゲーションについて次のように解説しています。
「ウェブサイトのナビゲーションは、訪問者が必要とするコンテンツをすばやく見つけるうえで重要です。また、ウェブサイトの所有者が重要と考えるコンテンツを検索エンジンが理解するのに役立ちます。Google の検索結果はページレベルで提供されますが、Google はサイト全体でそのページがどのような役割を果たしているかも把握しようとします。」
ナビゲーションはわかりやすい階層で、コンテンツから別のコンテンツへ、ユーザーができるだけ簡単にたどり着けるようにすることが大切です。
適宜ナビゲーション ページを追加し、内部的なリンク構造に効果的に組み込むことで、重要なページを検索エンジンに伝えたり、ページを閲覧するユーザーに関連ページへのリンクを提示したりできます。
避けるべきナビゲーションには次のようなものがあります。
SEOのヒント
・ナビゲーション リンクを複雑にする。
・サイト上のすべてのページを他のすべてのページにリンクする。
・コンテンツを過度に細分化する。
・読み込みの遅い画像やアニメーションに基づいてナビゲーションを作成する。
・スクリプトに基づくイベント処理を必要とするナビゲーションを作成する。
・無効なリンクのあるナビゲーションを放置する。
ユーザー向けのサイトマップページと、検索エンジン向けのXMLサイトマップファイルを作成することも有効です。
すべてのURLのリストを登録し、主要なコンテンツの最終更新日を記載するとよいでしょう。
有益な404ページを表示する
ユーザーが、無効なリンクをクリックするか、存在しないURLを入力してアクセスすると、404エラーページが表示されます。
ユーザーをサイト上の有効なページに導く親切なカスタム404ページを用意すれば、利便性を大幅に改善できます。
トップページやカテゴリーページへのリンクや、サイトマップ、サイト内検索などがあればユーザーは迷うことなくページを探すことができます。
パンくずリストを使用する
パンくずリストは、現在のページの階層を示す、内部リンク付きのテキストの行で、通常はページの上部に配置されます。
スターターガイドでは次のように解説されています。
「訪問者はパンくずリストを使って、前のセクションやルートページにすばやく戻ることができます。ほとんどのパンくずリストでは、最初の左端のリンクとして最も一般的なページ(通常はルートページ)を置き、右側に向けてより具体的なセクションを並べています。パンくずリストを表示する場合は、パンくずリストの構造化データのマークアップを使用することをおすすめします。」
パンくずリストはユーザーの利便性を向上させるだけでなく、上位階層などの重要なページに内部リンクが設置されることで、SEO効果を発揮できます。
内部リンクを上手に使う
内部リンクは、WEBサイトの他のページへのリンクです。
内部リンクでは上位階層、下位階層へのページ遷移のほか、関連するページをユーザーが見つけて移動できるようにする効果があります。
また、リンクを張るリンクテキストをアンカーテキストといい、リンク先のページ内容を適切に記述します。
避けるべきナビゲーションには次のようなものがあります。
SEOのヒント
・「こちら」、「記事」、「ここをクリック」などの一般的なアンカー テキストを記述する。
・リンク先のページのテーマから外れたテキストや内容と関連のないテキストを使用する。
・ページのURLをアンカーテキストとして使用する(URLが適切な場合もあります)。
・長いアンカーテキスト(長い文、テキストから成る短いパラグラフなど)を記述する。
・リンクを通常のテキストのように見せる CSS やテキストのスタイルを使用する。
・過度にキーワードが挿入されたアンカーテキスト、長いアンカーテキストを使用する。
・ユーザーのサイトのナビゲーションに役立たない不要なリンクを作成する。
画像を最適化する
画像ファイルは、一般的にサポートされているファイル形式、たとえばJPEG、GIF、PNG、BMP、WebP の各画像形式を使用します。
WEBサイトに掲載する画像の容量が大きいと、ページを開く動作が遅くなりユーザーフレンドリーではありません。
スターターガイドでは次のように解説しています。
「HTML要素imgまたはpictureを使用する
セマンティック HTML マークアップを使用すると、クローラが容易に画像を検出して処理できるようになります。また、
画像容量は、圧縮して軽減しておくことが効果的です。
imgタグには、画像のwidth, heightの数値を指定しておくと、レンダリング速度に好影響があります。
画像ファイルには簡潔でわかりやすいファイル名とaltテキストを使用する
画像にわかりやすいファイル名を付け、alt 属性で説明を記述します。
alt属性とは、なんらかの理由で画像を表示できない場合の代替テキストです。
altテキストは、画像をリンクとして使用する場合に、テキストリンクのアンカーテキストと同様の役割も果たします。
次のようなことは避けましょう。
SEOのヒント
・スパムと見なされるような長すぎる alt テキストを記述する。
・サイトのナビゲーションとして画像のリンクのみを使用する。
サイトをモバイルフレンドリーにする
スマートフォンやタブレットでのWEBサイトの閲覧が多い今日では、Google検索はモバイルファーストを基本としています。
PC、モバイルのいずれの端末でも快適に閲覧できるWEBサイトを制作することが重要です。
モバイルフレンドリーではないWEBサイトは、SEOの面から不利になる可能性があります。
モバイルフレンドリーなWEBサイトを制作するには、次の3つの方法があり、PCでもモバイルでも同じサイトが最適なデザインで表示されるレスポンシブWEBデザインが主流です。
- レスポンシブウェブデザイン(推奨)
- 動的な配信
- 別々の URL
レスポンシブWEBデザインを採用した場合には、meta name="viewport" タグを使用すると、コンテンツの調整方法をブラウザに伝えることができます。
モバイル対応サイトを作成したら、GoogleのSearch Consoleにあるモバイルフレンドリー テストを使用して、ページがGoogle検索の検索結果ページで「モバイル フレンドリー」として表示される条件を満たしているかどうかを確認できます。
Search Consoleでは、モバイルユーザビリティの問題を確認することができます。
ユーザーのサイトへのアクセス経路やサイトでの行動を分析する
SEO対策には、検索順位のチェックや、アクセス解析等によるユーザー行動の分析が不可欠です。
てSearch Consoleを使えば、検索パフォーマンス、ページエクスペリエンスの確認や、URL検査、サイトマップの送信などをすることができます。
また、Search Console Insightsを使えば、サイトへのトラフィックについて、人気のあるページや検索キーワード(クエリ)などを確認することができます。
「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」に基づくコンテンツSEO対策
キーワード調査を行い、SEO対策をするキーワードをピックアップする
コンテンツSEOは、WEBサイトに記事などのコンテンツを追加して、ユーザーが検索するキーワードの意図に合致したコンテンツの執筆等を行い、よりユーザーニーズに合ったコンテンツに更新する施策です。
自社サイトのテーマに合ったメインとなるキーワードを、Google検索や、キーワード調査ツールなどでピックアップし、検索ボリュームなどを調べます。
実際にキーワードの検索結果にどのようなページがランクインしているかも調査します。
キーワードには、ビッグキーワード、ミドルキーワード、ロングテールキーワードのように、検索ボリュームに応じた種類があります。
また情報を調べるインフォメーショナルクエリ、購入などの行動やニーズなどを示すトランザクショナルクエリ、具体的な商品、サービスや固有名称などを調べるなびげーしょなるクエリなどがあります。
キーワードをグルーピングし、WEBサイトの構成に割り当てる
キーワードの中には、「ショッピング」と「購入」のように、意味の似たキーワードもあります。
似通ったキーワードはまとめ、検索意図の目的などに応じて、分類します。
WEBサイトのツリー構造にキーワードを当てはめて、トップページはメインとなるビッグキーワード、各カテゴリーごとのディレクトリトップにはミドルキーワード、各ページにはロングテールキーワードのように想定し、キーワードに合った箇所にページを制作し、記事を執筆します。
コンテンツを最適化する
各ページごとに、想定されるキーワードに合った記事を執筆し、ページをデザインしていきます。
検索で訪れたユーザーがにとって、興味深く、有益なサイトにすることが大切です。
スターターガイドには次のように解説されています。
「人を引きつける有益なコンテンツを作成すれば、このガイドで取り上げている他のどの要因よりもウェブサイトに影響を与える可能性があります。ユーザーは閲覧したときに良いコンテンツだと感じると、他のユーザーに知らせたいと思うものです。その際、ブログ投稿、ソーシャル メディア サービス、メール、フォーラムなどの手段が使われます。」
クチコミによる自然な評判は、ユーザーからの良い評判を得て、他のWEBサイトからのリンクがもらえることもあります。
ユーザーニーズに応える
スターターガイドの「読者が求めているものを把握して提供する」の項目には次のようにあります。
「ユーザーがコンテンツを探すときに検索しそうなキーワードを考えてみましょう。そのトピックについてよく知っているユーザーは、よく知らないユーザーとは異なるキーワードを検索クエリで使用するかもしれません。」
「Google広告には便利なキーワード プランナーが用意されています。このツールを使用すると、新しいキーワードのバリエーションを発見し、各キーワードのおおよその検索ボリュームを確認することができます。また、Google Search Console の検索パフォーマンス レポートでは、あなたのサイトが表示される上位の検索クエリと、サイトに多くのユーザーを導いている検索クエリを確認できます。」
ユーザーの役に立つコンテンツを制作する
他のサイトが提供していない、新しい便利なサービスを創造することを検討しましょう。
独自性のない記事や、内容の薄い記事などは、専門性や信頼性がないとしてSEO面でも良い結果を生まないでしょう。
オリジナルの調査情報を記載する、面白いニュース記事を公開する、固有のユーザー基盤を活用するといった方法もあります。
体験談やインタビューなど、独自のコンテンツは価値のあるコンテンツです。
読みやすいテキストを記述する
WEBページは簡単に移動やスクロールができるため、読み飛ばされやすく、ユーザーに分かりやすく読みやすいことが大切です。
文章を簡潔にし、適度に改行や段落、見出しを入れ、重要なテキストには太字や箇条書きを入れるなどするとよいでしょう。
綴りや文法の間違いが多い、いい加減なテキストや、手間をかけずに作成されたコンテンツは専門性や信頼性がないと判断されるかもしれません。
画像、動画などのリッチコンテンツを記述する
文字だけのコンテンツは読みにくく、敬遠されがちです。
コンテンツの内容を補強し、視覚的にもわかりやすく見せるため、画像、図解、表などを使って情報を整理して提示できれば、ユーザーの利便性も高まります。
動画で解説できるコンテンツがあれば、動画を配信し、WEBページ内に埋め込むのも効果的です。
画像や動画も検索エンジンの検索結果に表示されることがあります。
WEBサイト運営者・著者のプロフィールなどを明記する
WEBサイトの運営者と、各記事の著者のプロフィールは、できる限り充実した内容で用意しておくとよいでしょう。
WEBサイトの運営者が誰なのか、運営者と著者が異なるときは著者はどのような人なのかは、Googleの「検索品質評価ガイドライン」でも重視されています。
WEBサイトの運営者情報は、別ページとして用意し、各ページからアクセスできるようにしておくとよいでしょう。
著者のプロフィールは、各記事の末尾などに記載する方法のほか、やはり別ページとして用意し、各記事の著者名からリンクを張る方法などが推奨できます。
経験・専門性・信頼性・権威性のあるサイト作りを心掛ける
経験・専門性・信頼性・権威性(E-E-A-T)は、Googleの「検索品質評価ガイドライン」でも重視されています。
スターターガイドでは、次のように説明されています。
「評価の高いサイトは信頼できるサイトです。特定の分野で専門性と信頼性に対する評価を得られるようにしましょう。
サイトの運営者、コンテンツの提供者、サイトの目的を明確に示してください。ショッピング サイトなど金銭の授受が発生するウェブサイトでは、ユーザーが問題を解決するための明確なカスタマー サービス情報を十分に提供する必要があります。また、ニュースサイトの場合は、コンテンツの責任者を明確に示してください。」
「専門性と権威性がサイトの質を向上させます。サイト内のコンテンツは、そのトピックの専門家が作成または編集するようにしましょう。たとえば、専門知識や豊富な経験を持つ情報発信者が書いた記事であれば、ユーザーは記事の専門性を理解できます。科学的なトピックに関するページでは、十分に確立されたコンセンサスを示すことが有効です(そうしたコンセンサスが存在する場合)。」
特にユーザーの健康や財産、安全、社会に害を与える可能性のある分野のトピックは、YMYL(Your monay, your life)トピックとされ、経験・専門性・信頼性・権威性(E-E-A-T)が必要とされています。
たとえばショッピング決済ページでは、安全な接続が保証されなければ、ユーザーはサイトを信頼できません。
検索エンジンではなくユーザーに合わせてコンテンツを最適化する
WEBサイトにユーザーがアクセスしてもらうためには、SEOは重要な施策です。
しかしSEOのためだけに施策を行うのではなく、ユーザーのニーズに合わせてWEBサイトを制作することが大切です。
スターターガイドでは、避けるべき事項について、次のように解説しています。
SEOのヒント
・ユーザーに付加価値をほとんどもたらさない、既存のコンテンツの焼き直しまたはコピーを掲載する。
・ユーザーにとっては迷惑で意味のない、検索エンジン向けの不必要なキーワードを大量に挿入する。
・欺瞞的な方法でユーザーからテキストを隠す一方で、検索エンジンに対してはテキストを表示する。
・コンテンツが不足しており、ページの目的が果たされていないページを避ける。
・インタースティシャルページ(コンテンツにアクセスする前後に表示されるページ)のように、気が散る広告を避ける
SEOに逆効果となるスパム的な施策については、Googleウェブ検索のスパムに関するポリシーに詳しく解説されています。
スターターガイドでは、
「高品質のコンテンツを作成するには、時間、労力、専門知識、才能 / スキルのうち少なくとも 1 つが十分にあることが必要です。コンテンツが事実として正確で、記述が明確で、内容が包括的であることを確認してください。」
とされています。
検索エンジンは常に進化し、時に大きな検索順位の変動が起こります。
アルゴリズムも完全ではなく、ときには納得できない検索結果が散見されることもありますが、検索エンジンが目指す方向性を知り、WEBサイトのコンテンツを充実さえ、ユーザーのニーズに応えられるようにすることが重要といえます。
関連ページ:
■このページの著者:金原 正道